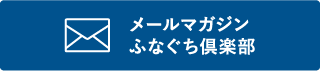陶磁器、漆器、金属や竹など、日本酒の酒器には色々な素材のものがありますね。今回は日文研収蔵の近代の「ガラス」製酒器をご紹介しましょう。
日本では、十七世紀にポルトガル人のもたらしたガラス製品の影響を受け、長崎で吹ガラスの製作がはじまりました。長崎で発達したガラスは、その後、京都・大坂へ、そして江戸へと伝播して、江戸では幾何学文様の切子ガラスが発展しました。さらに薩摩では藩の厚い保護によって、透明ガラスに紅色や藍色のガラスを被せ、幾何学文様をカットするガラス器が製造されました。このようにして近世日本においてガラスの輸入から美術的価値の高いガラス工芸が誕生するに至りました。

ガラス器にはちろりや徳利、杯など酒器も多く、当時舶来の貴重な酒であった葡萄酒や日本酒の冷酒などを愉しんでいたことが偲ばれます。ガラスという言葉は英語のGLASSが語源ですから、この語は幕末の開国後に欧米の各国と通商が行われてから使われるようになったものです。それまではガラスがビードロとかギヤマンと呼ばれていたことをご存じの方も多いことでしょう。明治時代になってからも、ビードロ、ギヤマンは広く通用していた言葉で、当時はガラスのほうがハイカラで耳慣れぬ言葉だったというのは、現代の感覚からするとなんだか不思議な感じもしますね。
ビードロ(VIDRO)はポルトガル語であり、室町時代の末期にポルトガル人が渡来して、そのものを持ってきてから日本で知られるようになった言葉です。江戸時代に編纂された類書(百科事典)である『和漢三才図絵』(正徳三年―一七一三年刊)には、「硝子」の文字を用い、これを「びいどろ」と読ませています。
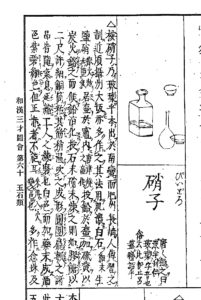
ギヤマンという言葉は少し後に出てきたもので、元来はガラスを意味する言葉ではないようです。
ギヤマンはオランダ語で宝石のダイヤモンドを示す言葉ディヤマン(DIAMANT)が語源です。ダイヤモンドでガラス器の表面をひっかいて模様をつける技法を長崎のガラス工人が学び、そのガラス器をギヤマン彫りと名付けて販売したところ人気となり、長崎土産に買って帰る人も出たそうです。つまり本当は「ギヤマン彫りのビードロ」なのです。ギヤマン彫りがギヤマンと短縮され、さらにギヤマン彫りのないものまでをギヤマンと誤って呼ぶようになったものと思われます。
ビードロというと、歌麿の浮世絵「ビードロを吹く娘」の印象が強く、薄い味わいの吹きものの器のことだと考える方が多いこと、また、ギヤマンというとキラキラした直線的なカットのあるガラス器を連想しがちなのは、語感からくるイメージからなのかもしれませんね。
ガラス製品が多く生産され、人々の生活の中に入り込んでいき、明治十六年頃からカット(切子)、グラビール(摺模様)、エッチング(腐食)、サンドブラスト(砂吹付法)など西洋式のガラス工法が全国的に広がったと云われています。近代日本のガラス製品は、現代の製品と比べると科学技術の発展途上のものといえますが、当時の新しい技術を貪欲に取り入れようとする職人の気概と大らかさ、またその工程の多くが手によるものならではの、温かみまで伝わるようなノスタルジックな魅力に溢れており、多くの蒐集家を惹きつけてやみません。
日文研ではガラス製の徳利や杯の他に杯洗も収蔵しています。


杯洗とは、杯の献酬(杯のやりとり)のとき取り交わす杯を洗うために使うもので、磁器・漆器・硝子などの鉢状の器です。今では見かける事の少なくなった杯洗ですが、江戸時代の酒の席を描いた浮世絵には必ずと言ってよいほど描かれている、いわば酒宴を彩る必須アイテム的な器だったのです。神聖な酒をひとつの杯で飲みあうことによって心と心が結ばれると信じられてきた日本ならではの道具といえるでしょう。実はこの杯洗、室町時代から始まった礼法が影響しています。室町時代の故実書である「家中竹馬記」(永生八年―一五一一年)に「杯の底を捨る事は魚道とて酒を残して口の付たる処すゝぐ也」とあり、それゆえに小笠原流礼法の『食物服用之巻』には「一露のみ」、「一文字のみ」と記載されています。「一露」とは一露で飲み口を洗うことを表し、「一文字」は一文字をかける程度の量でそれを洗うという作法なのだそうです。
さて、この杯洗二つとも「本当に杯洗?」という疑問も浮かびます。高坏(食物を盛る脚つきの器)との区別が一番議論を呼ぶところですが、この胴部の深さからいって杯洗に軍配が上がりそう…。ただこれが、例えば高坏やアイスペールであったとしても杯洗に「見立て」るのは日本人の得意技でしょう。戦国時代の茶人武野紹鴎が、井戸の水をくむ時に使う釣瓶を水指として用いたことも「見立て」。茶の湯初期の頃から「見立て」のお道具は多く用いられているのですから。「見立て」とは、「物を本来のあるべき姿ではなく、別の物として見る」という物の見方をいい、本来は漢詩や和歌の技法からきた文芸の用語なのだそう。この文芸の精神であった「見立て」の心を大いに生かして、日常の生活用品を茶道具に採り入れていたのですね。茶の湯だけではありません。落語でも扇で蕎麦をすする仕草を見せたり、日本庭園は石だけで水の流れを表現したりと、日本には見立てによってイマジネーションをふくらませる文化が根付いているのです。
酒器ひとつとっても、昔から大切に使われ長い時間を経て残ってきたものは、現代の私達に様々なことを教えてくれる存在といえるでしょう。
日本酒はその魅力のひとつとして、冷酒から燗まで『幅広い温度帯で飲むことができる』という点が挙げられます。同じお酒でも、その
温度によって味わいや香りは大きく変わります。その味わいの広さをもっと楽しみたいという思いが、様々な酒器を生んできたのでしょう。酒器には「大人の遊び心」が詰められてきました。

暑い季節には、ガラス素材の透明感やカットの輝きが器を見るだけで涼を感じさせ、それを手にして口を当てればひんやり感を直に感じ、中の冷酒の味わいをもうワンランクあげてくれます。季節や好みにより食卓の彩に、そして飲む酒の温度に合わせて、注ぎ飲む器を選ぶことが出来る楽しさは、日本酒好きに与えられた特権と思うのは、酒好きの贔屓目でしょうか。
〈参考〉
日本の酒器サントリー美術館
明治大正のガラス加藤孝次工芸出版
酒史研究第1
9号酒史学会編集
和漢三才図絵日本随筆大成刊行
小笠原流公式ホームページ
■デジタルブック「菊水通信」より