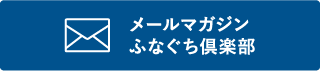今から50年前、皆さん何をしていましたか?
50年前1972年といえば……第一次田中角栄内閣成立、日本の鉄道開業100周年、沖縄が日本に復帰、札幌オリンピック開催、と日本が戦後処理の終盤を迎えつつ、近代化に向けて走り出していた頃、様々な出来事があった年でした。
そんな1972年にふなぐち菊水一番しぼり(以下ふなぐち)は産声をあげました。当時とても画期的な商品と言われたのですが、その背景はどのようなものだったのか、当時の清酒業界を知る手掛かりになる資料をみてみましょう。
日本醸造協会誌(1906年創刊の醸造に関する総合専門誌)の1972年1月発行である第67巻第1号に、当時の国税庁酒税課の担当者による「酒類行政と産業政策」の記事を見つけました。
そこに記されていたのは、清酒業界が「古い歴史を持つ在来産業」であること。これまでは「業界内に巨大産業が存在せず」、主原料である米が「長い間統制下におかれ」ていた為「生産シェアが固定化」されていたこと。上記の理由により「平均規模が圧倒的に零細であるにも関わらず、最近まで比較的平穏に推移することができ」ていたとのこと。
しかし此処に来て「需要の変化(消費の高級化・人口の都市集中・マスメディアの発達等)が重なりあって、いわゆる銘柄格差が顕著となり、販売面での上位集中が進んできたこと。「灘・伏見の主産地ブランドイメージ、特に高級酒としてのイメージが強い」ため、他地方の「中小企業の生きる途」は「思い切った合併、協業等により、早急に規模の利益、生産性向上を図る」か、もしくは「適正規模でありうるような分野を造出してそれへ特化すること」と断言されています。そして最後に「大企業による規模の利益が国民に還元されるとともに、中小企業もまた、そのあるべき場所を探りあて、大小が巧くバランスした状況が実現できれば、それこそ清酒製造業の最も望ましい産業構造であろう」と締めくくられています。
このように業界誌で官の立場より提言される程に、時代の変化とともに大手メーカーさんによる販売シェアが勢いを増していたこと、それにより地方の中小蔵元が厳しい状況に置かれつつあったことが読み取れます。
では、民の立場である業界各社はどのように時代を見ていたのか。同誌には 「21世紀の酒を語る」と題し、大手酒造メーカーさん、大手卸売会社さん等による新春放談も掲載されています。いわく、「現在清酒は生産過剰な状態にありますので、これから脱却するのには、嗜好の多様化に対応した商品の多様化というものを積極的に進めなければならないし」、「戦後は全体的に技術が向上し一定水準以上のものが多いので、その上の品質差は少ない」、「歴史的にみますと酒類で新製品というのはなかなか無いんですね。最近の新製品というのは飲料ではコーラ、ヤクルト、カルピス等ですが、それに引きかえて酒なんかで新しいものをときどきいろんな試みがなされておりますが、もう1 つぱっとしない」などの発言がありました。
戦後の技術向上により品質の良い酒を安定的に生産できている状況であること。特に大手メーカーが販売シェアで勢いを増している状況であること。その中でも多様化した嗜好に対応できる新商品が必要であること。他の飲料に比してアルコールには際立ったヒット商品が生まれていない状況に懸念を抱いていること、等々が読み取れます。
加えて、「新製品を作る場合に技術的にはいろいろな可能性はありますが、いまのコーラのように定着するまでの期間、それに対するいろいろな要素、例えば実際売るほうの力が大事です。いまのところでは、そこまで持っていく力の不足を感じさせられるんです」とありました。これからの販売促進方法にも思いを巡らせ、時代の大きな変化への対応に危機感を持っていたことがうかがえます。
また、「普通はかん(燗)して飲む」、新製品を出す場合「全部かん(燗)して決めます」とあり、当時、燗をつける飲み方が多数を占めていたことも示されています。
以上は中央の、国の機関の提言であり、業界を代表する大手メーカーさん、大手商社さんによる放談です。地方の多くの中小メーカーは、またそれぞれに違った状況にあったことでしょう。先の記事に共感する蔵もあれば、少し遠い世界の出来事のように感じている蔵、そもそも中央の動きを全く意識しない考え方など、様々だったことと推察しますが、大きく捉えると、1972年はこの様な時代背景であり、清酒業界の状況だったといえるでしょう。
前述の様な時代に、ふなぐちは生まれました。発売までに3年間の開発期間があったことを鑑みると、その先見性に驚かされます。
国税庁酒税課の提言にある「適正規模でありうるような分野を造出してそれへ特化すること」を、既に目指していたこと。そして新春放談にあるとおり、大手企業でさえ「酒なんかで新しいものをときどきいろんな試みがなされておりますが、もう1 つぱっとしない」状況であった中に、新潟という地方の小さな蔵が画期的な新商品を生み出したこと。何よりこれらが記事の出る3年前には着手され、記事が掲載された時には発売が開始されていたのですから。
開発のきっかけは、お客様の声でした。当時菊水では、蔵見学に来られたお客様へしぼりたての原酒を試飲していただいていました。その生の美味しさは、お代わりを求められたり、「買って帰りたい」とお声が多くあるほどだったのです。清酒は微生物の働きによって醸します。この微生物の働きを上手にコントロールするのが酒造りの大きなポイントの一つです。
商品として流通させるには品質を安定させることが必須、この工程が「火入れ」と呼ばれる加熱処理です。生酒の殺菌を行うとともに、残っている酵素の働きを停止させるのです。蔵でふるまっていたのはこの火入れをする前の生酒です。フレッシュでとても美味しいことは蔵の人間が一番よく知っていたのですが、酵素の働きを止めていない生酒、この後どう変化するか分からないものをそのまま容器に詰めて市場に流通させることはできません。
当時の社長である四代目・髙澤英介は常々こう考えていました。「良い酒を提供するのは蔵元の義務である。酒税法で規定する酒造免許は『一般には禁止されていることを特別に許可する』という趣旨であり、そこには『免許を持つ以上は良い酒をより多く世の中へ供給しなさい』という法の精神があるのだ」と。このような信念を持つ蔵元にとって、蔵でしか飲めないこの美味い生酒を、どうにかして多くの人々に届けられないか、届けるべきだと強い思いにかられたのは、必然だったことでしょう。
信念に基づいた強い思いであったとはいえ、実際に商品にするには様々な問題がありました。当時の若手蔵人を中心に一丸となって研究に取り組みました。従来の酒造工程を一から見直すのは勿論、使用する酒造機器、容器の素材、果ては容量に至るまで。どうしたらこの生酒の味わいを商品化できるか、その目的の為に熟考を重ね、試行錯誤を繰り返しました。
3年の研究期間を経て、生酒のフレッシュさを活かす為、火入れをせずとも酵素の働きをコントロール出来る酒造技術を見出しました。また容器には、ガラス瓶ではなく紫外線を遮断できるアルミ缶を採用することで生酒のデリケートさを損ねずに保てることにも辿り着きます。加えて、一升(1800㎖)瓶入りが常識だった当時において、200㎖という小容量にしたことも、しぼりたての酒をフレッシュなまま飲み切れる分量を意識しての選択です。かくして、火入れ殺菌をしない生酒、飲み切りサイズの小容量、アルミ缶入り、燗にしないばかりかキンキンに冷やして飲む、と当時の清酒の在り様を根底からひっくり返すような斬新な新商品が生まれたのです。

前述した1972年の新春放談の記事に、新しい商品を販売して定着させる難しさも語られていました。ふなぐちのユニークさはこの販売促進法にも表れています。販売促進のスタート地点として目を付けたのは、なんとスキー場でした。1960年代より日本国内はスポーツや旅行などのレジャーブームが巻き起こっており、1972年の札幌オリンピックをきっかけにウィンタースポーツ熱が高まり、その大衆化が進みました。スキーブームの到来です。多くの人で賑わうスキー場に目を付けたのですね。スキー客や温泉客が泊まる民宿の主人に、まずは試飲してもらい、今までなかった生酒の美味しさを知ってもらいます。

そして夕食のお膳にお酒をつけるには、一般的な一升瓶入りの日本酒では徳利に入れ替える手間がかかるし使用後は洗わなくてはいけないが、この商品ならこのままお膳に並べ、後片付けも楽であり、飲まない客は持って帰る事もできる。と、この新時代の酒の美味しさに加え、その利便性をも丁寧に説いて廻ったのです。然して、狙いは見事当たりました。採用してくれる宿が増え、首都圏から遊びに来ていた若いスキーヤーや観光客は宿で飲んだ新しい酒の美味しさを口コミで伝えるようになり、ハンディな缶入り酒はお土産としても喜ばれたのです。
スタートは山形の蔵王スキー場から、その後おなじ手法で越後湯沢、妙高高原、白馬などへ販促活動を拡げていきました。同時に、東京の百貨店に取り扱っていただける様に手を尽くしました。スキー場でふなぐちの味を知った若者が、帰京後に百貨店で購入できるようにしたのです。百貨店1社が採用してくださるに至り、そのユニークさと売れ行きに他の百貨店も追従してくださるようになりました。これでグンと販売量を伸ばすことに成功したのです。
蔵でしか飲めなかった酒を店で購入できるように、スキー場で出会った思い出の酒を首都圏でも買えるように。商品開発も販売方法も、「酒造免許を与えられているからには、良い酒を多く世の中へ提供する義務を負う」、蔵元の信念ともいえるこの思いから産みだされたものといえましょう。

実は、1966年67年と2年続けて菊水の地・北越後では集中豪雨で河川が氾濫し、歴史に残る大水害がありました。菊水の蔵も隈なく大量の土砂に覆われ壊滅的なダメージを被ってしまいました。そして、この水害を機とした県による河川改修もあり、菊水は立ち退きを余儀なくされているのです。その頃は従業員10名ほどの企業規模、2度の水害で蔵も設備も土砂まみれ、挙句に立ち退き命令。蔵元の心情いかばかりか、想像を絶するばかりです。それでも四代目当主は移転再建の道を選択し、資金面でも実務面でも語りつくせない苦難の中なんとか1969年に待望の新工場が完成、稼働させました。

この切羽詰まった状況下にあって常識では考えられない新商品ふなぐちを開発し、発売、思いも寄らない手法で販売促進活動を行い、これをヒットさせるに至るのです。
移転再建から発売まで、この間わずか3年のことでした。
この奇跡の様な商品ふなぐちは、発売から50年経てもなお、名実ともに菊水の看板商品です。発売から46年後の2018年には累計販売数3億本を突破しました。単純計算で1年に約650万本売れたことになります。200㎖入り高さ約10㎝のこの缶を、1年の販売本数を縦に並べたら650㎞。菊水から西へ直線距離で岡山と広島の県境あたり、北上すれば北海道富良野あたりまでに相当する長さ(いずれも地図上の直線距離)になります。お客様が買ってくださった本数の多さたるや、感謝の念に堪えません。

2012年には発売40周年を迎えました。ここまで飲み支えて下さったお客様に「直接」感謝をお伝えしよう!とご愛飲者様のご自宅へ菊水社員が訪問し、感謝の意と共に記念品をお渡しするキャンペーンを行いました。営業部門の担当者を筆頭に、事務方も製造部門も総出で。募集をかけ、「来ても良い」と応募くださった全てのお客様(北海道から九州まで)のお宅へ一軒一軒訪問したのです。このキャンペーン、お客様へ感謝をお伝えする目的だったのが、結果的に菊水が励まされることになりました。
飲み溜めた2年分の空き缶660本を玄関に飾って社員を迎えてくださる方あり、はじめて飲んだのはスキー場だったと、ふなぐちの歴史そのものの思い出を語ってくださる方あり、ご自身の営業活動の手土産として活用してくださっている方あり、訪れた社員が皆それぞれに、お客様のびっくりするようなエピソードを持ち帰ってきたのです。
他にも、同じ年の生まれといってふなぐちに親近感を持っていると笑う方、奥様のご実家である新潟へ結婚の挨拶に行かれた際に、ふなぐちが場を和ませてくれたという方、出張帰りの新幹線でふなぐちを飲み続けて20年という方、ふなぐちを売っていなかった近所のコンビニに頼み込んで取り扱ってくれるようにしてくださった方、子供の頃にお父様が美味しそうにふなぐちを飲んでいたことをきっかけにご愛飲いただくようになった方などなど。
社員が持ち帰ったエピソードを聞くにつれ、ふなぐちにはお客様それぞれの大事な思いが乗っていることに気づきました。長く販売されている商品には、その時間分、飲む方の人生や思い出が積み重ねられていくのですね。
50年前、蔵存続の大きな岐路に立ちながら、常識を覆す様な新商品を開発した当主の思い、その蔵元と新商品の可能性を信じて斬新な手法で販売活動を行った従業員、そして50年という長い間に飲んでくださった多くのお客様。ふなぐちが嗜好品としての日本酒、ただのロングセラー商品というだけではなく、立場の違い、時流を超えて、様々な人の想いを背負っている酒なのだと改めて感じ、感慨を深くしています。
お客様の思い出の中にある酒が、いつでもいつまでもお店に並んでいるということは、お客様の思い出を大切にすること。これを無くしてはいけないと強く思う次第です。
時を経て、販売する拠点はスキー場から全国の酒販店、スーパー、コンビニへ、ご愛飲者様との語らいは直接のご訪問からTwitterなどのSNSへ、様々に形は変わってもふなぐちという出来立ての美味しさをお届けしていく志は変わりません。50周年をヒトツの節目とし、ご愛飲者様への感謝を胸に、これからも菊水はこの酒を醸し続けて参ります。
【参考資料】
◆日本醸造協会誌第67巻第1号
◆菊水小史(菊水酒造株式会社発行)
◆NHKアーカイブス回想法ライブラリー自分史年表
https://www.nhk.or.jp/archives/kaisou/jibunshi/